「集団の中にいると疲れてしまう」
「空気を読むのが苦手で誤解される」
「特定のことに強いこだわりがある」
そんな日々の中で、
「もしかして自分はASD(自閉スペクトラム症)かもしれない」
と思ったあなたへ。
このページでは、自己理解から支援を受ける方法までをやさしく解説します🌱
① ASD(自閉スペクトラム症)ってどんなもの?
ASDは、脳の発達の特性によって生じるもので、以下のような特徴が見られます。
🔹 人との距離感がつかみにくい
🔹 予定外の変化に強いストレスを感じる
🔹 特定の物事に強い関心やこだわりがある
🔹 音や光など感覚に敏感または鈍感
ASDは「障害」というよりも“特性”のひとつ。多くの人が、自分に合った環境を見つけることで能力を活かしています。
② セルフチェックから始めよう🔍
まずは気軽に、自分の傾向を確認してみましょう。
✅ 集団行動や雑談が苦手
✅ 曖昧な指示では行動しづらい
✅ 音やにおい、肌ざわりなどに敏感
✅ ルールや順序に強いこだわりがある
✅ 興味のあることに集中しすぎてしまう
🌐「ASD セルフチェック 無料」で検索すると、【発達障害支援サイト】や【医療機関のチェックリスト】が見つかります。
※チェックはあくまで目安です。心配な場合は専門機関へ相談しましょう。
③ 専門機関で相談するには?🏥
不安を感じたら、心療内科・精神科・発達障害外来などへ相談してみましょう。
🔸相談〜診断の流れ(例)
- 初診予約(紹介状が必要な場合もあり)
- 医師との面談・ヒアリング
- 心理検査(WAISなど)を受ける
- 生育歴や日常での困りごとの確認
- 医師からの診断・フィードバック
📔 診察前に準備しておくとよいもの
- 困っていること・困ったエピソードのメモ
- 子どものころの様子(わかれば)
- 家族や職場での困難について
④ 自分に合った環境を整える🏡
診断を受ける・受けないに関わらず、「自分の特性を知る」ことは大切な第一歩です。
💡例えばこんな工夫が効果的です:
- 静かな作業スペースを確保する
- タスクを「見える化」して順序立てる
- 頻繁な予定変更を避ける
- 体調や感情の記録を習慣化する
👥職場や家族に自分の特性を共有し、サポートをお願いすることも◎
合理的配慮が受けられるケースもあります(診断があるとよりスムーズ)。
⑤ 使える支援やサービス📘
「誰に相談したらいいの?」と迷ったら、まずは以下のような機関へ連絡を:
- 🏢発達障害者支援センター(全国にあり)
- 🏛自治体の福祉窓口(障害福祉課)
- 📞地域の保健センター
- 🧑💼就労支援機関(就労移行支援など)
- 👨⚕️医療機関(精神科・心療内科)
必要に応じて、障害者手帳(精神・発達)や障害年金の申請も検討できます。
⑥ ASDの「強み」を活かそう🌟
ASDには「苦手なこと」だけでなく、「得意なこと」もたくさんあります。
✨ 一点集中力が高い
✨ 細かい作業が得意
✨ 独創的な視点を持っている
✨ ルールをきちんと守る
🔹 自分の“特性”を理解し、活かせる場所を見つける
🔹 ASDの当事者が活躍するコミュニティやSNSでつながる
自分だけのペースで、自分らしい道を見つけていきましょう🌈
📌まとめ:ひとりで抱え込まず、一歩ずつ
ASDかもしれないと思ったとき、最も大切なのは「気づいた今ここから」。
診断はゴールではなく、自分をよりよく知るためのヒントです。
あなたの「困りごと」や「生きづらさ」は、きちんと向き合えば必ず軽くできます🍀
必要なときは、周囲や専門機関に遠慮なく頼ってくださいね。

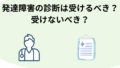
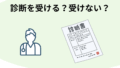
コメント