生きづらさとは、マイノリティーの積み重ねである
社会で感じる「生きづらさ」という言葉。これは多くの場合、マイノリティーであることから生じるのではないかと私は考えています。自閉スペクトラム症(ASD)を持つ私だけではなく、多くの人たちにとって、この感覚は日常生活の中で繰り返し体験される現実です。
つまりマイノリティーである思考や精神、行動、外見、所属する属性(集団)が多ければ多いほど「生きづらさ」を感じる場面が増えて深刻化していく。
逆に自分のすべての思考や精神、行動、外見、所属する属性(集団)がマイノリティーではない人はいないためにすべての人が多かれ少なかれ「生きづらさ」を感じているということです。
マイノリティーとは何か
ではマイノリティーとは、単に「数が少ない」という状況だけでなく、社会や環境の中で標準から外れているとみなされることを指します。特にASDの場合、感覚の過敏さや、独自の考え方、コミュニケーションのスタイルは、社会の「普通」とされる枠組みからずれやすい部分を持っています。その結果、社会の中で浮き彫りになり、周囲とのズレを感じることが「生きづらさ」として現れるのです。
積み重なるマイノリティーの例
ASDであること自体が一つのマイノリティーであることはもちろん、その他にも様々な要因が「積み重なる」ことで、生きづらさが増幅されることがあります。
1. 感覚過敏という特性
光、音、触感などに対する過敏さは、多くの人には理解されづらいことがあります。日常生活での些細な環境でもストレスが蓄積し、自分だけが「異なる」と感じる瞬間が増えます。
2. コミュニケーションの困難さ
会話の中で、意図を伝えるのが難しかったり、周囲の微妙なニュアンスを読み取れないことがあります。こうした体験が重なることで、人との交流に壁を感じやすくなります。変に同じ日本語話者のため、意味合いが通じているとお互いに認識してしまうことでミスコミュニケーションが増えていると感じます。そのため前提知識を揃えてからコミュニケーションをすることが必要です。
例
- その言葉をどういう意味・意図で使っているのか。
- 前提として共有していることは何か。(前提知識、状況把握、条件、目標)
3. 社会の標準からの逸脱
「普通」に振る舞うことを求められる場面が多い中で、自分らしく生きることが困難になる場合があります。例えば、ルールや慣習に柔軟に適応するのが難しい場合、結果的に「適応できない」と評価されることが少なくありません。
ASDのこだわりや黒白思考による影響が大きいですが、私の場合は合理性があるかないかの黒白思考が強いため、合理性と併せて説明できる社会標準なら守れます。逆に合理性がなく、感情的なことや惰性で続けていることは平気で無視してしまう傾向にあります。
4. 追加の社会的アイデンティティ
ASDであることに加え、他のマイノリティー性(宗教、性別、性的指向、民族的背景など)が重なることで、更に多層的な生きづらさが生まれることもあります。
この生きづらさを軽減するためには
マイノリティー性の積み重ねが生きづらさを生む一方で、それを解消する道筋も存在します。まずは自分自身と向き合い社会との摩擦を観察しましょう。いつ、どこで、どのように摩擦やミスコミュニケーションが発生するのか。まずは知ることから始める必要があります。
自己理解の促進
まず第一に自分自身が「自分の強みや特徴」を理解し、「周りとの違い」を認識することから始まります。その中でASD特有の「こだわり」等がどのように働いているかを知りましょう。
自身の役割を全うする
これは私の処世術ですが、その場での自身の役割を果たすことに100%全力を出す。そしてそれ以外のことは気にしないと言い聞かせる。自身にコントロールできないことを手放すと「生きづらさ」は軽減されます。
例えば、会社での役割。業務内容に100%集中し、噂話や人の悪口には参加しない。ただし業務を円滑に進めるために必要な雑談や関係性をキープする程度の人付き合いは必要。私的な交流は不要かもしれないが、持ちつ持たれつな業務上の助け合いは必要。
社会生活において、自身の役割を果たしていると攻撃されにくいことは確かにあります。逆に役割を果たしていないとそれだけで攻撃の対象になるのは身の回りでよく起きている出来事でしょう。(政治家が会議で居眠りしている等)
そのため自身に求められる役割をいち早く突き止めて、その役割を果たすことに集中しましょう。
対話と理解を深める場の提供
ASD当事者と非当事者ではミスコミュニケーションが発生しやすいです。そのためミスコミュニケーションや摩擦が生じた時は時間をかけて、お互いの認識をすり合わせることが必要になります。ただし当人同士で話し合いが不可能なときは、第三者に緩衝材として入ってもらうか、カウンセリング等を利用しましょう。
まとめ
生きづらさは、単に一つの要因から生じるのではなく、多層的なマイノリティー性の積み重ねから生まれることが多いと感じます。ASDを持つ私たちは、その複雑な現実を日々感じながら生きています。しかし、それを悲観するのではなく、社会の中で多様性を尊重し、理解を広げることで、少しずつ生きづらさを軽減できる道を築いていきたいと願っています。
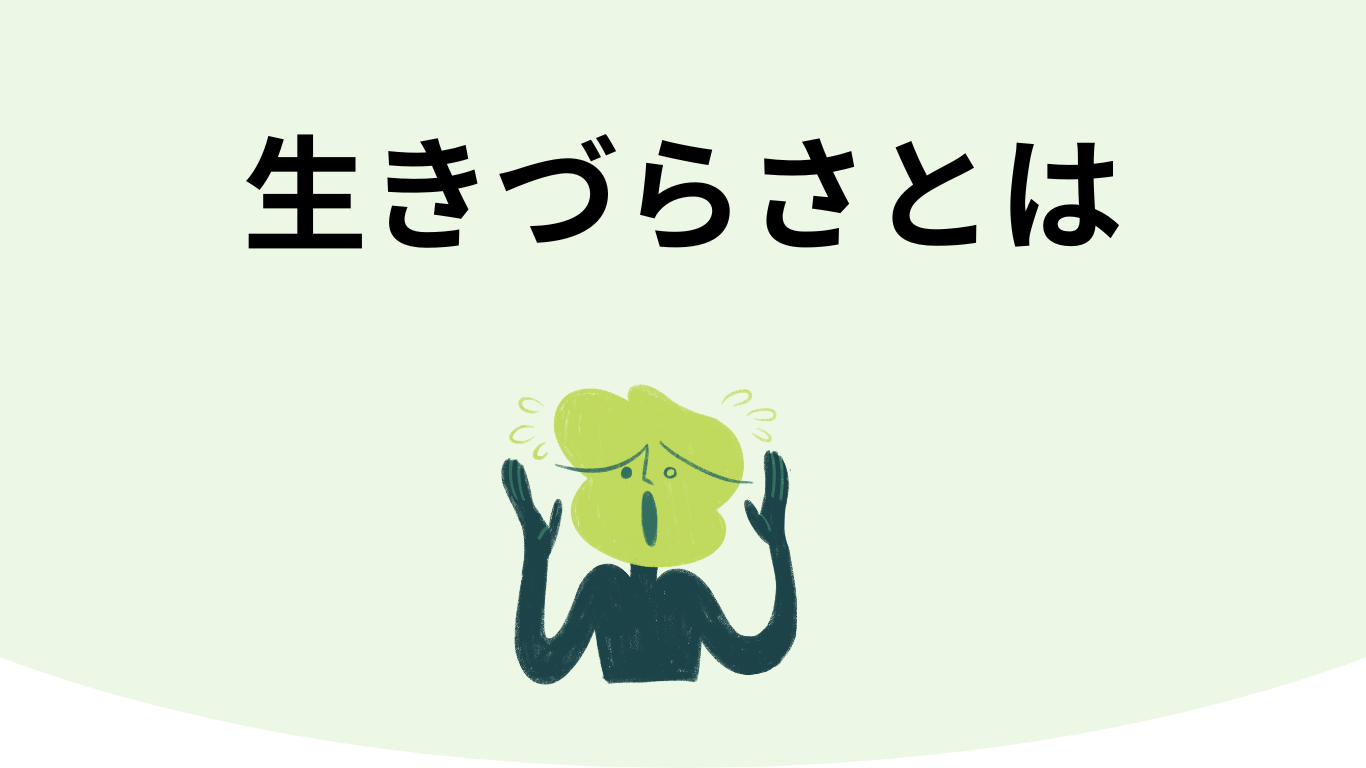
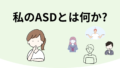
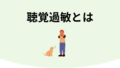
コメント