ASDと食事:興味の幅が限定的な特性が引き起こす課題
ASDを持つ人々が食事に対して独特な嗜好や選択をすることは珍しくありません。これには「食事の興味が限定的」という特性が影響しており、日常生活や健康において課題を引き起こすことがあります。
基本的に多くの人にある「好き嫌い」と同じですが、その困難は日常生活や健康に致命的な問題を引き起こすことがあります。
例えば、
私の場合「食事という動作」に対して嫌いという感情があります。
これによって生じる問題は
・常に低体重で、健康診断では「痩せ」を指摘されても、1年をとおして毎日3食取ることができない。(1日3食の日が週に3回程度、また外食して1人前を食べることができない)
・食べる回数と量を減らし過ぎて、起き上がることができないことがたまにある。低血糖症の症状(手足の震え、力が入らない)が出る。
対策として、常にベッドの横にブドウ糖と水分を置いている。また外出時も同様にブドウ糖と水分を常備。
食事における具体的な課題
1. 限られた食品の好み
ASDを持つ人の中には、特定の食品や味、食感への強い好みや嫌悪感を持つ場合があります。例えば、同じ種類の食品ばかりを好む「偏食」の状態が長期的に続くことも。
2. 栄養バランスの問題
食事が特定の食品に限られることで、栄養バランスが偏る可能性があります。例えば、果物や野菜をほとんど食べない場合、必要なビタミンやミネラルが不足するリスクがあります。
3. 社会的な場面での困難
食事の選択肢が限定的である場合、外食やイベントでの食事がストレスの原因となることがあります。メニューに自分が食べられるものがないと、強い不安を感じることも。
問題への対策とアプローチ
1. 段階的な食品導入
新しい食品を少しずつ試すことで、食事の幅を広げることが可能です。例えば、慣れた味や食感に似た新しい食材を加えてみるなどの方法があります。
2. 感覚に配慮した調理
食事の食感や見た目、匂いなど、感覚への影響を考慮して調理することで、食べやすくなる場合があります。例えば、つぶつぶした食感が苦手であれば、スムージーの形に加工するなど。
3. 代替栄養素の提供
栄養が偏る場合には、他の食品やサプリメントを活用して不足を補うことも選択肢の一つです。
4. 周囲の理解と支援
家族や友人、学校、職場がASDの特性を理解し、食事の選択を尊重することで、プレッシャーを軽減できます。
まとめ
食事に関して「興味の幅が限定的」という特性が課題をもたらすことは事実ですが、工夫とサポート次第で改善や対策が可能です。それぞれの特性やペースに応じた柔軟なアプローチが重要です。
頭で必要なことがわかっていても、実行できないのが一番の問題です。そのため実行できる範囲で代替手段を見つけるのが一番の解決策だと思います。
私の場合はカロリーメイトとサプリメントで対策しています。
|
|
|
|
食べる動作を少なくして、でも必要な栄養素を摂取できる。
こういった代替できるものを探して、日常生活に支障がでないように工夫してみてください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3b1ba0c9.421d7dc6.3b1ba0ca.c5286d6e/?me_id=1394074&item_id=10000991&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fk-relight%2Fcabinet%2Fthum1%2Fimgrc0093114139.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/474f3b21.419e631a.474f3b22.8f8d4589/?me_id=1270693&item_id=10007398&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fseedcoms%2Fcabinet%2Fimages%2Fthum%2F1m%2Fmvm_1m.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
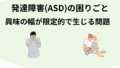
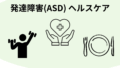
コメント