ASD(自閉スペクトラム症)の人は、苦手なことと得意なことの習熟度の差が大きいことがよくあります。この現象は、脳の情報処理の仕組みや認知の特性によって説明できます。
ASDの人の習熟度の差が大きくなる理由
1. 情報処理の偏り
ASDの人は特定の情報を深く処理する能力に長けている一方で、特定の情報を処理する能力が低く。そのため広範囲の情報を統合するのが苦手なことがあります。そのため、興味のある分野では高度な習熟度を示す一方で、苦手な分野では習熟が進みにくい傾向があります。
2. ワーキングメモリの特性
ワーキングメモリ(作業記憶)の使い方に違いがあり、得意なことに関しては情報を効率的に保持し、活用できるのに対し、苦手なことでは情報の整理や保持が難しくなることがあります。苦手な分野に関してはそもそも情報を認識できない、実行できない可能性があります。
3. 興味の限定性
ASDの人は、特定の興味に強く集中する傾向があります。このため、興味のある分野では繰り返し学習を行い、習熟度が高まる一方で、興味が薄い分野では学習のモチベーションが低くなり、習熟が進みにくくなります。
4. 感覚過敏・鈍麻
感覚の過敏さや鈍さが影響し、特定の活動に対する快適さが異なるため、得意なことには積極的に取り組めるが、苦手なことにはストレスを感じやすく、習熟が進みにくいことがあります。
ASDの特性を活かすために
習熟度の差をうまく活用するためには、以下のような工夫が有効です。
・得意な分野を伸ばす:興味のあることを活かせる環境を整える。
・苦手なことを補う工夫:自分の不得意なことから、代わりの学習方法を取り入れる。(教科書の文字を読むのが苦手なら、動画や音声学習に切り替える等)
・ストレスを軽減する:感覚過敏に配慮した環境を整えることで、苦手なことへの取り組みを促す。
自身の特性(得意・不得意)を理解し、適切な方法を選択することで、不得意なことを練習してできるようになれるかもしれません。
まとめ
私の場合聞こえすぎるせいか、学校の対面式の授業が苦手でした。もちろん他にも苦手な要因はいくつかありましたが。
そのため一人で教科書を読んでいるほうが、学習効果は高く。一人で勉強することが向いていました。
また不得意なことは諦めるのも手です。
そのかわりに何かしらののツールで代替するか、誰かに代わりにやってもらう等の手段を構築してしまうのが建設的です。
例えば、計算が苦手なら得意な人にしてもらう。(委任)
覚えられないなら忘れてしまうなら、メモやリマインドをする。(ツール)
自身の役割を果たすことに徹して、それ以外に自身の労力を割かないように工夫すると社会生活での負担は少なくなることと思います。
お互い血反吐吐きながらでも、頑張りましょう。
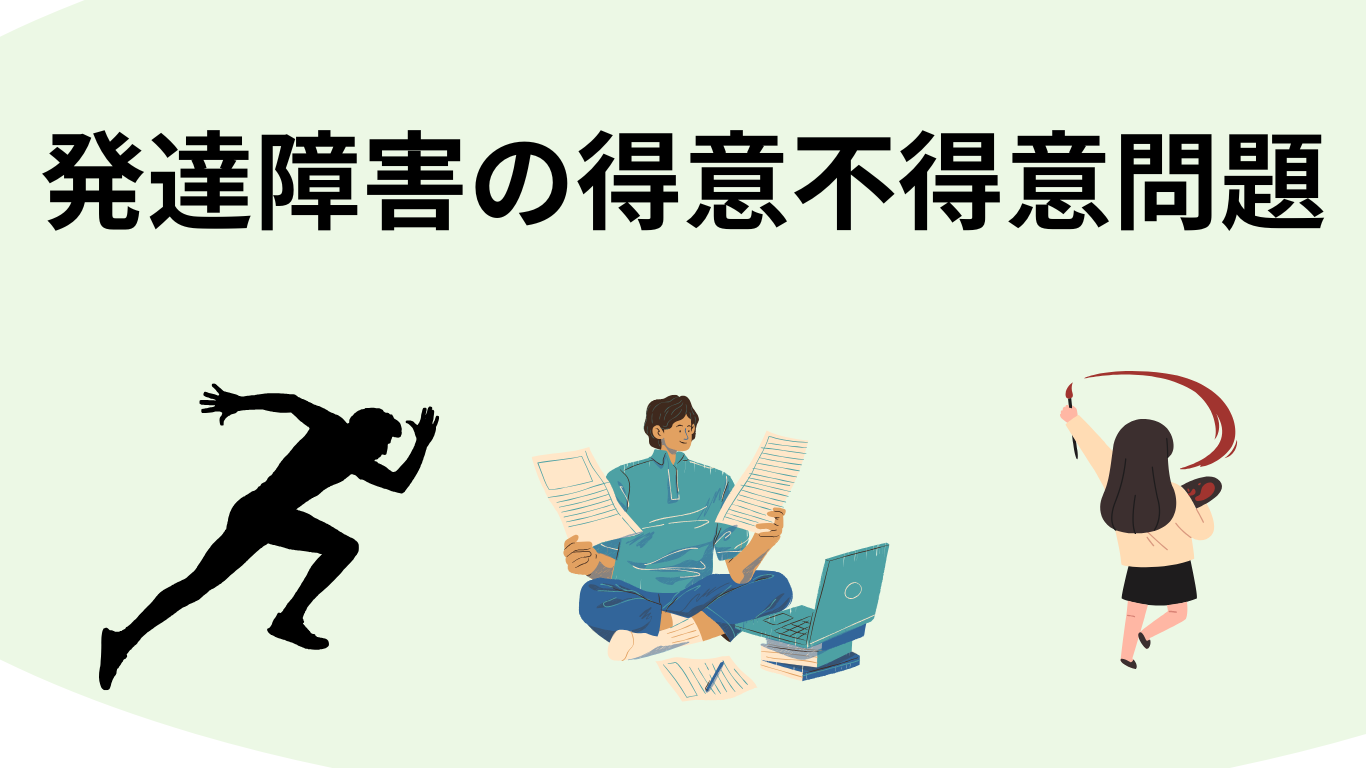

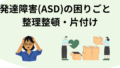
コメント