ASDと「興味の幅が限定的」という特性について
「ASDを持つ人の興味は限定的」という考え方は、時には誤解を招きやすい表現かもしれません。それは決して「狭い」だけではなく、「狭く深く」になる傾向が高いということ。
その一方で多趣味な人、つまり「浅く広く」がいるのも事実。あくまで「狭く深く」になりやすい傾向にあると考えてください。
例えば、ある人が特定のテーマに非常に強い関心を持つ場合、そのテーマについて驚くほど詳細な知識を持っていることがあります。これは、典型的な学習方法とは異なる可能性があるものの、その深さと専門性が特別で価値のあるスキルとなることもあります。
特性の背景
ASDの特性として、特定の事柄に強く集中する傾向があります。これは感覚の鋭敏さや、社会的な刺激に疲れやすいことから、自分にとって安心できる活動により多くの時間を費やすことと関連している場合があります。
この違いは安心領域を越えるために必要な、心理的な体力や安心して休める環境が充実しているかどうかの違いのように思います。
周囲の理解を深める方法
興味の深さを尊重し、広げる機会を作ることは重要です。
例えば
– ASDを持つ人の得意な分野をサポートし、それを活かして新しい分野との接続を試みる。
(抽象度を上げて、得意分野と新しい分野の共通点や類似点を提示して、新しい分野に誘導する)
– 周囲の人が興味の対象を共有し、交流の場を作る。
(自分とは異なる視点からの、知識や解釈を仕入れる機会を作る)
まとめ
興味の範囲が限定的だと感じられる場合でも、それを新しい視点から見ることで新たな可能性が広がるかもしれません。大事なのは、本人の特性を活かしながら、自己表現の場を広げることです。
特に私の場合は、自分の中からは決してでてこない「解釈や視点」を仕入れることが好きです。
それらを仕入れることによって、多角的に物事を見ることに喜びを感じるから。
ただしASDの特性上、自分の解釈や意見が絶対に正解でそれ以外を受け付けない方もいらっしゃいます。
理屈や理論で説明しても関係なく。そういた特性の方には意見等を押し付けるのではなく、「私はこう思うよ」程度に伝えるのでいいかと思います。伝える必要がなければ無理に伝える必要はないでしょう。本人もパニックになる可能性があるので。
大事なのは本人の特性に寄りそうこと。感情やいろいろな理由(社会的に○○だから、正解は○○だから)はASDの人には響かないことが多いです。(私にとって価値のない言葉、響かない言葉であることは事実)伝える必要がない場合は無理に伝えなくてもいいし、どうしても必要なときは煩わしいかもしれませんが、理屈で説明してみましょう。少しは説得できる可能性が上がるかもしれません。


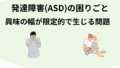
コメント