ASDと興味の幅が限定的で生じる問題
ASDの特性として挙げられる「興味の幅が限定的」という点は、深い集中力や専門性を生む可能性がある一方で、日常生活や社会との関わりの中でいくつかの課題を引き起こすことがあります。
例えば以下のことが上げられます。
社会で求められているスキルや知識を習得できない、習得することに困難がある。(自ら習得しにいけずに、苦労する。習得するまでが苦痛で我慢できない)
視野が狭く、物事同士のつながりや多方面から見ることができない。(物事の1面しか見ることができない)
社会で問題が具体化すると
- 社会的孤立: 興味が特定の分野に限られる場合、周囲の人々と共有できる話題が少なくなり、孤立を感じることがあります。これが社会的交流へのハードルを高める要因となることがあります。
- 柔軟性の欠如: 特定の事柄に固執するあまり、新しいことへの挑戦や変化に対応することが難しくなる場合があります。これにより、学校や職場での適応が難しくなることも。
- 視野の制限: 深い興味を持つ一方で、その分野以外のことに目を向ける機会が減り、多様性や新しいスキルの習得が妨げられる可能性があります。
- 誤解の発生: ASDを理解していない人から「融通が効かない」「偏りがある」と誤解されることで、対人関係が損なわれる場合があります。
解決策やアプローチ
-
- 支援を提供: ASDを持つ人が安心して新しいことに挑戦できる環境を作る。
- 興味を広げるための工夫: 深い興味を他分野へつなげる形で、学びや活動の幅を広げる。
- 社会的交流を促進: 興味を共有できるグループやコミュニティへの参加をサポート。
以上の3点に共通することは、視野を広げるということ。視野を広げて共通点と相違点を見つけることに注力しましょう。
周りの人は、「これにはこういう面があるよね」等の気づきを与えることで、本人に気付きのきっかけを提供して欲しいと思います。(無理にする必要はありません。立場的にしないといけない場合のみ)
視野が狭いと指摘されたことのある人は、まず2つの物事にある最小の(唯一の)共通点を探すようにしましょう。
あるいは、相違点。いつもと違う点や他の物とは違う点を探してください。
また手っ取り早く視野を広げる方法は、自分と他の人の共通点と相違点を見つけることです。
同じものを見て、他の人の感想や考察にある「自分との共通点と相違点」を探してみましょう。
まとめ
「興味の幅が限定的」という特性は課題を生むこともありますが、それを理解し、適切に対処することで日常生活や社会的関係をより良いものにすることができます。この特性はしょせん道具にすぎません。この特性があるから「生きづらい、生きやすい」が決まるわけではありません。要は使い方の問題。そのためこの特性をどう扱えばいいのか、この道具の使い方をマスターすることに集中しましょう。
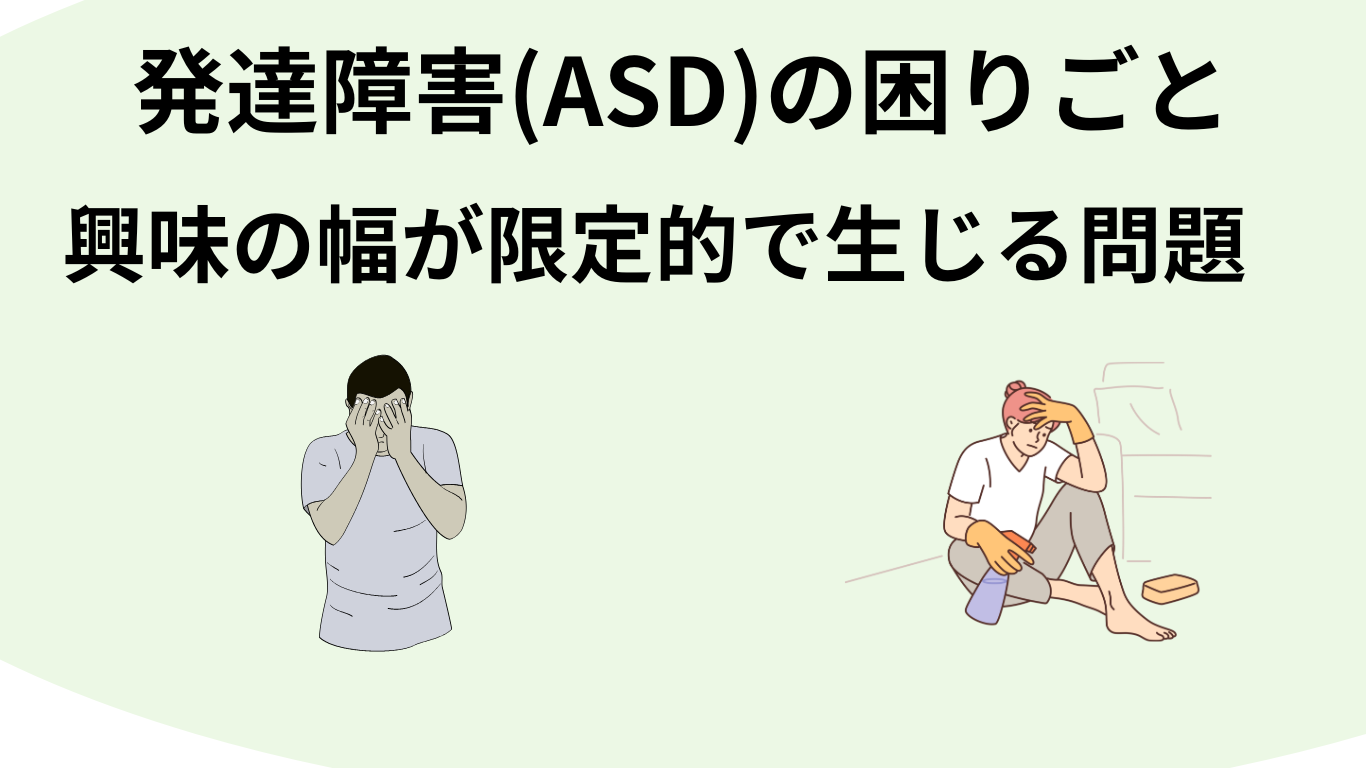
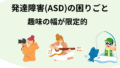
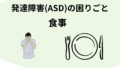
コメント